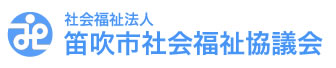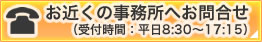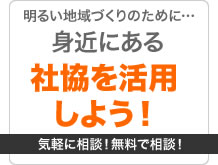まりなです![]()
昨日は南アルプス市で行われた、市職員と社協、市内事業所の皆さんを対象とした研修会へ参加しました。内容は「社会福祉協議会が行う権利擁護」というタイトルです。
この研修会の講師は、なんと支援センターふえふきの職員である、萩原学です![]()
萩原は今、成年後見(法人後見含む)や市民後見普及、日常生活自立支援事業、その他の権利擁護をいかに活用していくかというとても難しい仕事をこなしています。![]()
実は社協でこのような事業に関わる所は少なく、先人の知恵をぜひにもという意向で南アルプス市から依頼をされたのです。となると後輩の私としても、先輩の応援をすべく、また私も学ばなければということから同行させていただきました。
![]()
講義の中心は、社協の立場の復習、日常生活自立支援、法人後見の取り組み等を分かりやすく説明。今から成年後見に取り組もう、また日常生活自立支援事業を活用していこうという人を対象とした話をしました。
会場からは、それら制度利用の成果や、法人後見を受ける意味は、等の質問があり、皆真剣に聞き入っていました。また、同行した鈴木からも業務での関わりを紹介する場面もありました。
成年後見や日常生活自立支援事業は、本人の権利擁護の点ではとても大事な道具になります。
しかし、直接に接する社協職員は擁護(その方の権利を守る)する事と同時に、権利侵害の可能性もあるという両刃の剣になることも。例えば認知症のご老人が衝動的にお金を使いたいという欲求にかられて生活が成り立たなくなる。そこは制度でしっかりと擁護していく必要はあるでしょう。でも、そのお金は本人の物であり、使いたいという本人の要求は権利でもあるのです。うーむ・・・。
また、社協が法人後見(後見人は親族、または弁護士や司法書士、社会福祉士が受けることが主ですが、法人が受任し、職員が動くことも可能です)をすることの意味も質問としてあげられました。
それと、チームで動く、連携を作っていくことの大切さを萩原は訴えています。
チーム作り・・・・なるほど。
私の感想とすると、質問でもあげられていましたが、実際にこの制度を使って、良かったケースをもっと知りたかったです。今回は実際に利用されている2人のケースを紹介して説明していましたが、南アルプス市での実際の話はもちろん、広く色んな現場の皆さんの話を聞きたかった。
と言う訳で、とても難しいものではなく、もっと身近な制度であるよう、福祉職員だけでなく、広く皆さんにも参加して頂いて、支援の輪が広がっていくことが大切なんだなと思っています![]() 。
。
こうやって笛吹市の社協が他の市へ依頼されて講演する。これってすごい事なんだと、改めて自分の職場を自慢します。![]() 今後も沢山の所で講演依頼が来ると良いな
今後も沢山の所で講演依頼が来ると良いな![]() 。
。
では・・・まりなでした。