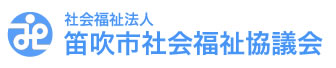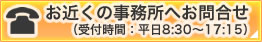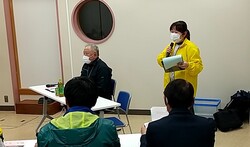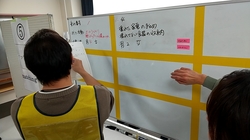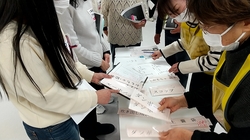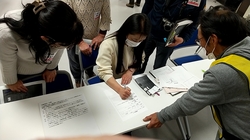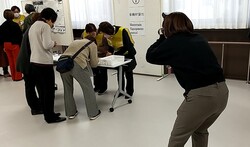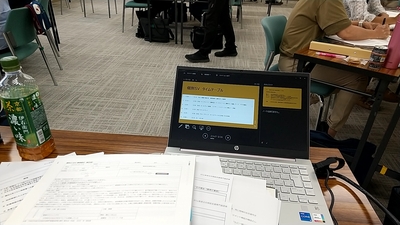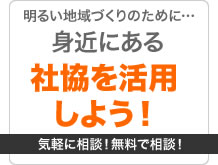2月2日は日曜日でしたが、笛吹市のボランティアさんが自主開催した学習会である、防災ボランティアの訓練に参加しました、その時の職員の動きを中心にお知らせします。内容に関しては、担当者からの報告をお待ちください。
さて、社協は地震などの災害時には、災害ボランティアセンターを開設することになっています。東北でも、最近は能登の地震と大雨の際に、多方面から来るボランティアの確保や整理。流れ込んだ泥を撤去すること、家の瓦礫を出すなどの力仕事だけではなく、炊き出しだったり、配食のお手伝いだったり、支援物資の配分と、ボランティアへのニーズはとても多く、またその必要としているところに必要人数を配置するなどコントロールセンターとしての機能が重要になります。被災時には、行政であっても、警察や消防の職員まで、同じ地域の方は全員が被災者であることを意識しての助け合いが必要となります。
コロナ前は笛吹市の清流公園で実施されたり、コロナ時でも県の防災ボランティア訓練はありましたが、ようやく再開しました。御坂の生涯学習センターには多くの市民が集まり、設置の訓練を行いました。
今回は主に企画運営した職員だけではなく、住民さんと同じ視点で職員もボランティアとして参加していました。そうはいっても、いざとなれば職員もボランティアセンターで皆さんと協働を企画運営する立場になります。
会場は前日から乗り込んで設置していたとのこと。前回の防災ボランティア訓練から間が空きすぎてしまっているため、資材や書類、手順なども始めての事業のようだったようです。大勢の人が、それも一般の方が集まるイベントは、労力の8割が準備に費やされます。
開始1時間前には早くも来場者が居ました。それだけこの学習会への興味や熱量が高い証拠です。準備が間に合わず職員も走り回って調整しています。
開会の挨拶や、県社協からの講師である和田さんの基礎的な講義が13時30分から始まりました。
講義の後には、災害時を想定した模擬訓練を行う流れになっていますが、この時にも訓練がスムーズに進むよう、準備する資材を求めて職員は動き回っていました。
講義も終わり、いざ模擬訓練です。今回は参加者をAとBのグループに分け、センターの運営側と、ボランティア参加者の模擬を1回ずつ行います。
ところが、最初から大混乱の会場。黄色を身に着けたAグループの方がセンター運営スタッフとなるのですが、自分が何をすべきかが分からない、また職員も的確な指示が出せない。なぜなら、職員ですら体験したことが無いのです。コロナで間が空いてしまったこと、異動や退職の都合でキャリア形成が難しかったことで、全員が困惑状況。でも、これは実際の被災地でも同じでしょう。ここから訓練が出来たことはとても大きな資源です。企画運営する職員は、経験者と共に各担当者を回り、繰り返し説明をしています。
これからBグループのボランティア役が会場に入ってきました。
こうやってAとBを交互に行いました。最初は全員が戸惑って、各ブースに人や仕事が滞ってしまい、時間ばかりかかってしまいましたが、時間を追うごとにお互いが慣れてきて、最後はスムーズに流れていました。
またこの日は山日新聞の取材が入りました。逆取材です。
という訳で、担当した職員の動きを中心にお伝えしました。コロナで間が空いてしまったとはいえ、実際の災害時には更に混乱することが予想されます。今や、防災は地区防災が主です。皆さんの地域を皆さんが守る、そして、ボランティアをする、受ける、調整するなども含めて、誰かがやる、ではなく、自分も出来るという自信を、日頃から重ねる必要性を感じています。本当に、職員ですら、大慌てなのですから。
過去に行われた防災ボランティア設置訓練のブログ記事です。
また、山梨県で行われた設置訓練に、障がい当事者もボランティアとして参加した際のブログになります。
どんなことをやっているか分からない、という方。笛吹社協は防災ボランティアに関しての推進を行っております。各地域事務所まで、お問い合わせください。