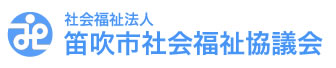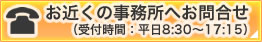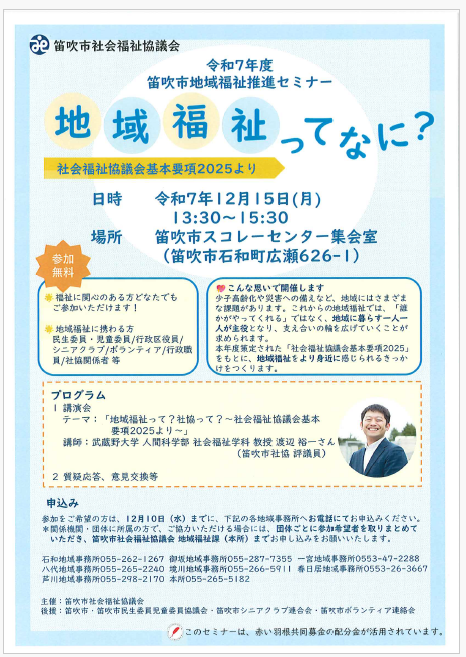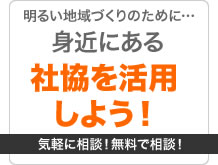富士見小学校からの依頼を受け、6年生65名を対象に福祉についてお話をさせていただきました。


福祉というと「困っている人」「かわいそうな人」「障がい者や高齢者」などのためのものと考えられる傾向がありました。
私たち社会福祉協議会は、福祉(ふくし)とは、「ふだんの くらしを (自分らしく)しあわせにくらす」ことを実現していくことと、子どもから大人の皆さんに説明させていただいております。
児童が捉えるかわいそうな人や障がいのある人だけに関係するものではなく、みんな=自分にとっても大切なことであるということをお伝えしました。
『 あなたにとっての幸せってなんですか?』
最初のワークで聞いてみると、
「友達と遊んでいるとき」
「家族と過ごしているとき」
「ゲームをしているとき」
「おいしいご飯を食べているとき」
など、たくさんの意見を出してくれました。
みんなの幸せを聞いてみると一人ひとりその内容は違っていることがわかると同時に、聞いた周りの人にまで自然と笑顔が広がってワクワク楽しい気持ちや幸せなき気持ちになりました。
その幸せは、自分一人の力で成り立っているのではないことも気づいてもらえたことと思います。
生まれたばかりの赤ちゃんでも、障がい者でも高齢者でも、先生でもお父さんお母さんでも、地域のおじさんおばさんでも、みんな幸せに生きる権利があります。
それぞれの人にとっての「幸せ」を認め合うこと、自分の幸せだけではなくお友達や周りの人にとっての幸せ、みんなにとっての幸せを大切にすることが福祉につながるということを、お伝えさせていただきました。
次に、身の周りの福祉について具体的な例示やクイズをしながら楽しく学んでもらいました。
日頃、何気なく目にしている地域の中や、生活の身の回りの物にも福祉のデザインや工夫がたくさんつまっていることに気づいてくれたことと思います。
また、今までの生活の中でどんな人が関わってきてくれたか、今の自分にはどんな方が関わってくれているか。そして、今日ここにいるみなさん一人一人も地域の中の一員ということや、見守ってもらうだけではなくて何かできることがあるか考えてもらう時間になりました。
最後に「福祉」のお仕事のひとつとして、社会福祉協議会の仕事に就いてもお話しさせていただきました。福祉のしごとや社協についても興味を持ってくれて、
「どうして福祉の仕事をしようと思ったのですか?」
「どんなお仕事があるのですか?」
「笛吹市社会福祉協議会では何人働いているのですか?」
「大きなイベントもやっているのですか?」
などと、たくさんの質問をしてくれました。
今日お話を聞いてくれている子どもたちの中から、もしかしたら、将来、地域で一緒に働くことができる日が来るかもしれません。
今日考えた自分にとっての幸せと、20年後、30年後の幸せは違ってくるかもしれません。
同じように、年を重ねることでできる事やできない事も変わってきます。
それでも、一生を通して幸せに生きることができるように、人と人とが関わりながら、時に助けてもらったり助けたりしながら、お互いのことを理解しあい暮らしやすい地域にしていきたいですね。
未来ある子どもたちの貴重な45分の授業に関わらせていただくことで、一人一人の想いや行動が人を支え、よりよい地域をつくっていくことを子どもたちと一緒に考えさせていただいた時間となりました。
*笛吹市社会福祉協議会では、地域のみなさんからいただいた貴重な社協会費を財源
に、 市内の小学校・中学校・高校を対象に福祉教育の推進事業を実施しております。