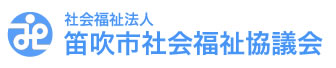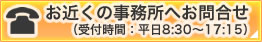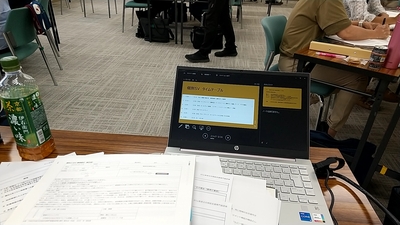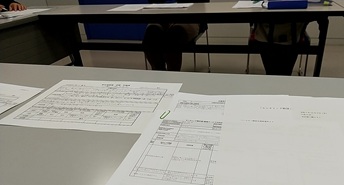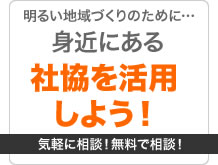引き続きこの1か月の様子をお知らせします。
3,主任相談支援専門員研修でスーパービジョンの講義を担当しました。
障がい児者の様々なサービスのケアマネジメントだけではなく、様々な困りごとに対応する専門職として、相談支援専門員がいます。今や、高齢者の介護保険同様、障がい福祉のサービスも利用計画が必要となっています。
相談支援専門員になるためには、まず初任者研修を受講し、5年毎に更新をする目的で現任研修を受講することで、引き続き専門員の業務が出来ます。そして、サービスのマネジメントだけではなく、その地域の福祉の向上となる調整を行ったり、地域の中での人材育成を図ったりする役割として、現任研修終了後のキャリア育成としての主任相談支援専門員が設置されました。
その主任相談支援専門員を育成するための研修に、講師として参加しました。
さて、スーパービジョンという言葉を知っていますか? スーパービジョンは人材育成の方法として様々な場面で活用されています。例えば諸外国では、医師や教師、専門職等の感情労働者は必ず指定された時間や方法でスーパービジョンを受けたり、カウンセリングを受ける義務を設定されています。残念ながら日本ではこのスーパービジョンが定着化していません。スーパービジョンを行う人をスーパーバイザーと言います。
社会福祉士会では、このスーパーバイザーを認定制度にしており、ジチョーも認定スーパーバイザーでもあります。ちなみに現在、山梨県では認定を受けているのは13名。大学の教授をはじめ、各福祉分野で活躍されている方が担っています。
この日は演習。事例に沿って、受講者の方々と協議をします。しかし、やはりというか、スーパービジョンの意義がなかなか伝わらない。こういうことは地道に積み上げていくことが求められています。
まあ、社協の中ですら、ジチョーはスーパービジョンは依頼されませんからね。難しいです。
4,社会福祉セミナーに参加しました。
7月5日、6日の土日は、鉄道弘済会の社会福祉セミナーに参加しました。講義のテーマの一つはケアラーです。ヤングケアラー支援が注目され、山梨でも県が主になっての支援体制構築を進めています。ケアラ―として支援を提供する側の視点や、当事者でありながらも支援を続ける方々など、様々な点での講談を聞きました。
記念講演として、「コーダの僕が活きる世界」の講演を聞きました。コーダとは、両親が聴覚障がいであるような家庭であり、小さい頃から通訳的存在としての子どもを担っている方で、その役割を果たすことが過重になってしまう傾向にあります。昨年では「コーダ あいのうた」という映画が、世界的ヒットしました。歌手になる夢と、その才能を評価されても、聴覚障がいの家族から離れて生きていけるかというテーマでした。
いずれもリアルな講演で、障がい者はケアを受けるだけの存在ではないこと等の思い込みをしている自分に気が付きます。こういった方々が社会に出て自分の意見を言える世の中であることが大事です。
この他にも色々とありますが、この辺で。大事なことは学び続けることだと実感します、