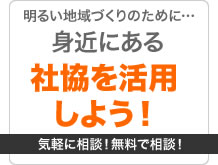山梨県笛吹市社会福祉協議会のサイトです。
山梨県笛吹市社会福祉協議会のサイトです。

AIデマンド交通の「のるーと笛吹」が、今年の4月より
運行エリアを拡大し春日居町からも乗れるようになりました。

そこで、春日居ふれあい工房のメンバーが
初めてのるーと乗車にチャレンジした様子をレポートします![]()
まずは予約から!
今回の目的地はドン・キホーテとはま寿司です![]()
メンバーの中から代表を決めてコールセンターへ電話します![]()
▲スピーカーにして周りのメンバーも真剣に聞いています。
事前に皆で確認しておいたので、
オペレーターの案内に従い、スムーズに予約ができました![]()
================================
当日は春日居ふれあい工房のメンバー6名と職員が乗車しました![]()
なかには車いすユーザーのメンバーさんも![]()
職員が介助者として付き添い、乗降のお手伝いをします。

▲乗り口の段差が高く、介助は2人がかり
▲ステップはありますが、入り口が広いため手すりが両手では掴めず...
支払いは運転手さんからの指示により代表して1名のメンバーが![]()
次はみんなが体験できると良いですね。
ドン・キホーテ内では各々で行動しました![]()
車いす利用者のメンバーに、他のメンバーが付き添い、
支え合いながら和やかにおふたりで買い物をしていました![]()

▲レジの精算も手の届かないところはサポートしています
昼食は回転ずし![]()
タッチパネル注文や、カウンター席での食事など、
はじめてチャレンジする方もいました
帰りものるーとに乗ります。

この日は猛暑日![]()
乗降ポイントで待つ間も暑すぎて、お隣の薬局さんの店内で
待たせていただきました。
健康館サワ石和店の皆さん、急遽のことに親切に
ご対応いただきありがとうございました![]()
たくさんの支え合いとチャレンジがあったと有意義な1日でした![]()
この経験を自信にして、日常生活でものるーとを活用し
行動範囲を広げていってもらえたらと思います。
メンバーの皆さんからは、
「ひとりだと勇気が出ず、出来なかったかも。
でも仲間がいてくれたので出来たし楽しかった。」
「暑かったけど久しぶりにワクワクしました。」
「回転ずしも初めてでたくさん食べちゃいました。おいしかった。」
との感想がありました。
地活3型では社会生活訓練の場として、
メンバーの皆さんの希望や社会の動きに合わせて
今後も柔軟に様々な体験の機会を提供していきます。
活動に関心のある方はいつでも覗きに来てくださいね![]()


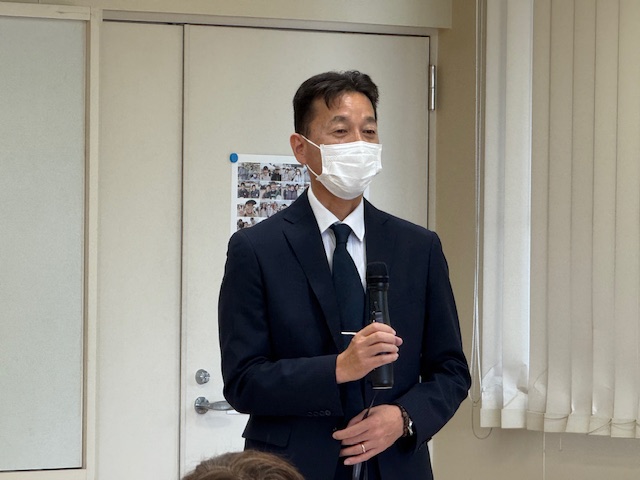

6月9日 横浜市泉区中田地区民生委員、児童委員の方が見学にみえました。
竹内会長の挨拶、依田施設長の施設概要説明後、木村管理者が障がい部門の説明をさせていただきました。午前中の見学だった為、お風呂はディ利用者様が使用しており、すぐに障がい部門の作業見学となりました。急な機材トラブルにも見舞われ、慌ただしい朝でしたが、無事見学者をお迎えすることができ本当に良かったです。
木村管理者が、各々の仕事のブースを周りながら説明をさせていただきました。 この日は、傘拭きやノバキャップのお仕事に加え、農福連携のお仕事として、地元の農家の依頼で全国の顧客に送るパンフレットの封筒入れを行なっていました。
何枚もあるパンフレットを枚数、順番をチェックしたものをクリアファイルに入れ、宛名シールを貼ったA4版の封筒に入れていきます。
資料と封筒を裏返しにセットする事で、封筒に入れ易くなります。
ちょっとした工夫ですが、これをすることでミスを減らし、作業効率を上げることができます。
また、体験コーナーとして、紙粘土を丸めて作る"まんまるマグネット"の模様付けも行いました。 事前にメンバーさんが作り、乾燥させたもの模様をつけていただきました。
【まんまるマグネット制作風景】
※紙粘土を7グラムに計り、ひびが入らないように水をつけながら丸めて乾燥させます。
見本を真似しながら描く方やオリジナリティを発揮される方等様々で、とても盛り上がりました。 模様付けされたものはお土産としてお持ち帰りいただきました。お帰りになる際とても楽しかったと大勢の方に行言っていただけました。
質疑応答では、どのような経緯で農福連携の事業を始めたのかとの質問があがり、スマイルいちのみやの前身である3型事業所"一宮夢ふうせん"の頃からパンフレットの封入の仕事は直接依頼を受け行なってきた。スマイル開所時、県の農福連携を強化する動きの中で、声をかけていただき、桃の摘蕾などの畑へ行く仕事をするようになったと説明させていただきました。
見学会最後の販売会では、かえで支援学校から実習にきていた生徒さんも売り子さんとして参加しました。なかなか恥ずかしくて元気な挨拶とはいきませんでしたが、学校では味わえない経験ができたのではないかと思います。
たくさんのジャムや小物をお買い求めいただきました。 全額メンバーさんの工賃となります。ありがとうございました。






5月26日に日本釣振興会の主催により、石和南小学校の4年生29名が、笛吹川でアユの稚魚の放流体験をおこないました。この活動は、地域の子どもたちに魚のことや水辺の環境の大切さを知ってもらうことを目的に開催されていて、今年で5回目になります。
最初に山下市長より、「笛吹市」という名前は笛吹川の川の名前をいただいていること、笛吹川は市の真ん中を通っていて果実を作るにも生活を営むにも昔から恩恵をいただいていることなどのお話がありました。
また、日本釣振興会山梨県支部長の雨宮さんからは、アユについての説明や笛吹川をはじめとする自然環境のお話、放流の説明などがあり、子ども達は真剣な表情で聞きいっていました。
説明を聞いた後、子ども達はアユの入ったバケツをひとつずつもらい、約4400匹の稚魚を放流しました。たくさんの数なので1回では終わらず、何度も土手を駆け上がっていました。
「放流前にアユに触ってみてもいいですよ。その時は、まず自分の手をバケツの中の水で冷やしてから優しく触ってくださいね。」
雨宮さんが説明してくださったとおりに、魚の命を感じながらそっと触ったり、「元気に大きく育ってね!」と優しい言葉をかけていました。放流した後も、元気に泳いでくれるか心配そうに見守っている表情が印象的でした。
日本釣振興会では、「豊かな水辺環境を次世代へ」というテーマを掲げ、稚魚の放流だけでなく、水辺の清掃活動や釣りのマナー教室など、SDGsに貢献する地域活動を行っているそうです。 私自身も放流を通して、魚や環境について考えるきっかけになりました。
つなげよう、つたえていこう、温かい心、いさわ
支え合う地域づくり 石和