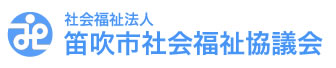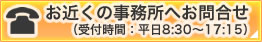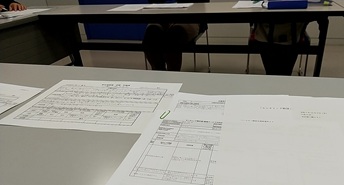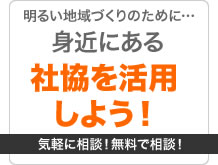6月12日の山日新聞の「かいじネットワーク」に、ジチョーの記事が掲載されました。それも結構大きめの記事であり、ジチョーも驚いております。
なぜ、取材を受けることが出来たのか。それは「ジチョーのふらふらあるき 合理的配慮とはこういうのもあります」(5月14日公開)
を、山日新聞の記者の鈴木さんが目に止め、合理的配慮って何だろうと思ってくれたことからでした。
ブログを公開してまもなく、記者の鈴木さんから連絡があり、取材をさせていただきたいという連絡が入りました。その前にも、笛吹社協のイベントの取材に来てくれたこともある記者さんで、積極的に色々と取材をしていただけました。
最初はブログにある、障がい者差別のことから説明をしました。ブログには作業をしているAさんがヘッドホンを付けて音楽を聴きながら作業をしていることが、なぜ合理的配慮となるのか等の説明をしました。
その内、ジチョーの経歴にも触れていただき、介護職から相談支援の職に移ってきた経緯、認定社会福祉士(※1)や精神保健福祉士(※2)などの専門資格も働きながら取得していったこと。ジチョーも交通事故の怪我の後遺症で障がい者であること、仕事の中だけではなく、自分の体験でも障がいへの理解がまだまだ広がっていないことなどを時間を掛けて聞いていただきました。
1回の取材では終わらず、何度か電話でもジチョーの意向を確認していただき、掲載される前日にも連絡をいただきました。
新聞に掲載されたことで、早速記事の内容についての様々な相談がありました。差別を受けた当事者から、或いはその関係者という相談です。それ以外にも、実に多くの方々から「新聞、見たよ」と声を掛けていただいたのです。
改めて新聞掲載の効果が分かりました。山日新聞の記者の鈴木さん、ありがとうございました。
新聞にも書いてありますが、まだまだ障がい理解が少ないと感じることがあります。ジチョーが障害手帳をもったのは約40年前。ジチョーにとって苦手なのが「和式トイレ」。いわゆるしゃがむことがとても辛いのです。当時は和式トイレが中心で、例えばコンビニですら和式トイレでした。それが今やどこでも洋式トイレになり、場所によっては広い多目的トイレもあるようになっています。なぜか。
それは、不便さへの理解が進んだからであります。障がいだけではなく、足腰が弱くなった方も自宅に閉じこもらず、外に出るようになったから。不便さへの共感を高めるためには、不便を感じている方々がその不便さを発信すること。「いつかは自分も」という共生の意識が大事になります。障がい者の環境だけが良くなることではなく、全ての地域の住民のための意識が大切になります。
ちなみに、この障がい者に関わる事業や、社協の各種活動はジチョーだけが実施している訳ではありません。書面の都合で、ジチョーの紹介が主になっています。笛吹社協職員の頑張りを代表しての取材と捉えていただけるとありがたく思います。
※認定社会福祉士とは
高度な知識と卓越した技術を用いて、個別支援や他職種との連携、地域福祉の増進を行う能力を有する社会福祉士としてのキャリアアップを支援する仕組みとして、実践力を認定する「認定社会福祉士制度」を創設。山梨県では6名が登録。
※精神保健福祉士とは
専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者。現在、93544名が登録されている。