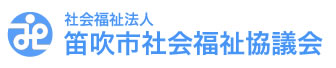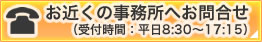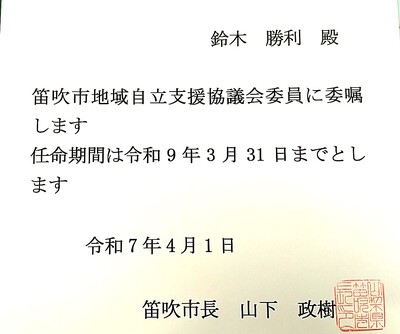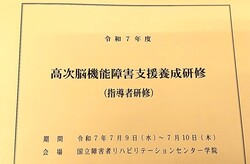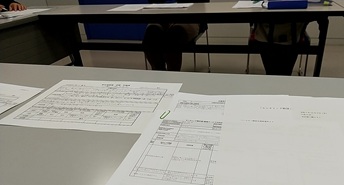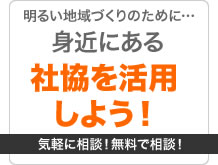6月になり、いよいよ7年度の様々な事業が動いています。そのバタバタに飲み込まれて、ブログの更新も1か月無いままに過ぎてしまいました。いくつかの研修や事業のことを紹介します。
1,6月27日 笛吹市自立支援協議会 本会が実施されました。
自立支援協議会は、笛吹市内の障がい福祉に携わる様々な機関や個人が集まり、協議を行う場です。サービス事業所の代表や、県の委託を受けた事業所、弁護士さん、学校の先生、そして市の障がいに関する職員、高齢、児童、生活保護に関する職員などが参加しています。年度が変わったこともあり、新しく委嘱を受けました。
今回の協議は、前年度の事業を振り返りつつ、7年度の事業をどのように展開していくか、が主になります。
ジチョーはまた相談支援部会を担うことになります。相談支援部会の昨年度の活動は、別のブログを参照してください。今回はそのひとつを紹介。
その他にも、障がい者虐待に関する事例の整理や提言。また、支援センターふえふきの活動の紹介や、先日、山日新聞に掲載されたこと等も皆さんに発表しました。また1年、笛吹市の障がい福祉の向上の為に頑張ります。
2,高次脳機能障害支援者研修講師養成研修に参加しました。
「高次脳機能障害」と言う言葉を知っていますか?
人間の脳は、全身を上手に動かすこと、生きていくための機能をコントロールするなどを司る大事な機関です。この脳はひとつしかないのですが、その部位によって働きや役割が分かれています。
食べる事や呼吸する、排せつ等、最低限必要な機能だけではなく、記憶する、見て判断する、話すことでコミュニケーションを取るなど、人間社会に適合するよう、とても高度な役割を担う部位があり、これら高度な部分の脳が損傷を受けてしまうことがあります。例えば脳血管障害。脳の血管が詰まる、出血をすることで、脳の一部機能が破損してしまいます。また頭を大きくぶつけるような事故があると、同じように脳が破損してしまいます。体を動かす機能が破損すると、麻痺が起こります。そして、高度な機能を発揮する部分が壊れてしまうようなこともあります。この人にとって高度な脳の機能を「高次脳」と言い、そこに障がいが起きることを「高次脳機能障害」と表現します。
問題は、この高次脳機能障害は外見だけでは分からないことも多く、見逃されてしまう障がいでもあります。それは当事者、家族も同じで、事故や病気発症をきっかけに物忘れが酷くなったり、性格が変わってしまった、集中しにくくなったなどの症状に苦しんでいる人は少なくないのです。
この障がいへの理解と、就労や生活の場での困りごとに適合できる支援者を増やすために、昨年から高次脳機能障害の支援に当たる職員を育成する目的で研修制度が始まりました。その講師を担うための研修がこの講師養成研修です。
ジチョーがこの高次脳機能障害の方の問題に携わったのは20年以上も前の事です。当時はまだ一部の専門的な医師くらいしかこの障がいを理解する人も居なかったため、独学で勉強をしました。それがようやく誰でも学べる場が出来たのです。
と言っても、この研修は4日間に渡る内容。教える方も教わる方も大変です。でも、とても勉強になります。皆さんも学んでみませんか?
ちょっと長くなってきましたので、後半はまた別のブログで紹介します。